小麦と植物油をやめれば、生理も更年期障害も軽く過ごすことが出来る。もう一つ乳タンパクのカゼインも。よしりんさんが言っていたことです。残念ながらエビデンスはありません。それはエビデンスのレベルが追いついてないからだと思います。実験期間が極端に短く、有意差が出るまで検証していないからでしょう。
粗大ゴミ は 中国にお返しします pic.twitter.com/9WsLXoKTd0
— 369不動 (@N4er5BANKPkQFQe) November 25, 2025
jurian🌸 @juri_piyo 尾身茂さん、 2025年11月.この時期になってまだ コロナワクチン被害を 陰謀論(説)呼ばわりするのは さすがに、もう…🤷♀️ 『コロナワクチン💉による被害(死亡)、 残念ながら日本では 詳細なデータを取れるシステムになってない』 ヤル気のない、 こんないい加減な者が 分科会会長と呼ばれ、 311億円もの補助金を意のままにし、放置してる事実 🤷♀️
尾身茂さん、
2025年11月.この時期になってまだ
コロナワクチン被害を
陰謀論(説)呼ばわりするのは
さすがに、もう…🤷♀️『コロナワクチン💉による被害(死亡)、
残念ながら日本では
詳細なデータを取れるシステムになってない』
ヤル気のない、
こんないい加減な者が
分科会会長と呼ばれ、… https://t.co/pRshIZ0GHF pic.twitter.com/43vXyxE3kA— jurian🌸 (@juri_piyo) November 24, 2025
この”COVID-19ワクチン誘発性心停止症候群”…..
あなたの周りで急死した人、思い当たることはありませんか⁉️ https://t.co/ucqgGWQXQX— 池田としえ (@toshie_fujisan) November 23, 2025
トッポ @w2skwn3 🚨【ワクチンで心臓が止まる…⁉️】 ついに明かされました。 “COVID-19ワクチンによる心停止” この新たな症候群が、医学的に完全定義されたのは今回が初めてです📉 研究チームが指摘したのは… 💉ワクチン接種によって引き起こされる心筋炎が、 ・心臓に永久的な損傷を残し ・微細な瘢痕(マイクロスカー)を形成し ・それが突然死の引き金となるという衝撃のメカニズム💥 しかもFDAは今もこの事実を認めていない。隠蔽に手を貸しているとまで指摘されています。 これまで「一時的な炎症」とされてきたワクチン後の心筋炎、実は目に見えない“心臓の火種”を残している可能性があると… 研究者たちは声を上げています。 これは“たまたま倒れた”や“別の要因”と片づけられる話じゃない、と。 この”COVID-19ワクチン誘発性心停止症候群”….. あなたの周りで急死した人、思い当たることはありませんか?
🚨【ワクチンで心臓が止まる…⁉️】
ついに明かされました。
“COVID-19ワクチンによる心停止”
この新たな症候群が、医学的に完全定義されたのは今回が初めてです📉研究チームが指摘したのは…
💉ワクチン接種によって引き起こされる心筋炎が、
・心臓に永久的な損傷を残し… pic.twitter.com/r0hwXibzbX— トッポ (@w2skwn3) November 21, 2025
コミュニティノート、「何言ってるのかよくわからない」ですね。 https://t.co/98UCW4ibEl
— 森田洋之@医師・community Dr./医療経済ジャーナリスト/「医療」から暮らしを守る/音楽家 (@MNHR_Labo) November 23, 2025
小林製薬、梅肉エキス製造子会社の梅丹本舗を解散 「紅麹」響き債務超過に – 日本経済新聞 https://t.co/iydUiLhbeR😭😭😭
国はワクチン薬害を調査せず、小林製薬のせいにしてでっち上げて、子会社の梅丹本舗を潰した😭😭😭
許せない‼️😡😡😡— まるこまる (@marukomaru777) November 23, 2025
小林製薬、梅肉エキス製造子会社の梅丹本舗を解散 「紅麹」響き債務超過に – 日本経済新聞

小林製薬は8日、梅肉エキス製品を生産していた子会社の梅丹本舗(和歌山県紀の川市)を12月末に解散すると発表した。小林製薬の旧大阪工場から梅丹本舗の工場に紅麹(こうじ)原料の製造設備を移管していたが、健康被害問題の発覚後に操業を止めた。梅肉エキス製品の生産も停止し、債務超過に陥っていた。
小林製薬が梅丹本舗に対して保有する債権の一部を放棄し、債務超過の状態を解消した上で吸収合併する方式を取る。小林製薬は「完全子会社との合併であり、連結業績に与える影響は軽微」と説明している。
梅丹本舗の工場は6月末に閉鎖した。同社の2024年12月期の単独決算は、税引き損益が4億7500万円の赤字(前の期は8595万円の赤字)だった。
ワクワクさん、まだいたんですね😁 https://t.co/Al7xhd1sTK
— 森田洋之@医師・community Dr./医療経済ジャーナリスト/「医療」から暮らしを守る/音楽家 (@MNHR_Labo) November 23, 2025
非営利で独占て、
わかりやすい‼️
子宮頸がんワクチンをずーっと公明党と共に推進続けたフローレンス‼️駒崎👊 https://t.co/XlK0KNSiqf— 池田としえ (@toshie_fujisan) November 23, 2025
日本を守れ‼️
立ち上がれ日本‼️
報道は外資、
横に繋がり語ることを諦めるな‼️ https://t.co/BOnr2p9mYY— 池田としえ (@toshie_fujisan) November 23, 2025
Katsuhiko Fukuda MD PhD 福田 克彦 @eitchan ケビン・マッカーナン博士のスピーチ(後半を抜粋): 日本では、現在、超過死亡率が広島の津波の合計を超えていることがわかります。 これはワクチン接種プログラムと一致しています。 そして、日本はワクチン接種を遅らせているにもかかわらず、有害事象は減少していません。 国民の約13%がこれらのワクチンのうち7種を接種しました。 私の発表が終わるにあたって指摘しておきたいのは、 日本で発生している癌の種類は、これまでのものとは異なるということです。 そしてそれらは、これからの私たちも注意を払う必要がある兆候であり、偶然に起こっていることではありません。 (「チェラン・ダグラス保健区への科学発表: クリニックからCOVID-19ワクチンを撤去する取り組み」より抜粋)
ケビン・マッカーナン博士のスピーチ(後半を抜粋):
日本では、現在、超過死亡率が広島の津波の合計を超えていることがわかります。
これはワクチン接種プログラムと一致しています。
そして、日本はワクチン接種を遅らせているにもかかわらず、有害事象は減少していません。… pic.twitter.com/fM00gv657f— Katsuhiko Fukuda MD PhD 福田 克彦 (@eitchan) November 22, 2025
「かかりにくい」人ほど神経質な対策はしていないという事でしょうか?やはり大事なのは、心身の健康を保つこと。年中マスクが健康にいいはずはない。
唾液が少ないとかかりにくいなら、余計に口呼吸の原因のマスクは逆効果。「インフルエンザの「かかりやすさ」その差は唾液にあった 2020/01/22」 pic.twitter.com/9c6kOhoipN
— Mr.NonWoven (@MrNonwoven) November 23, 2025
この記事ですね。https://t.co/URlDtsBY3u
このシリーズで手の洗いすぎへの警告もありました。ういう研究には鋭敏に反応しています。— しゅん(高木俊介) (@ragshun) November 24, 2025
※ 唾液の分泌量が少ないとインフルに罹りやすく、感染対策を良くすることは意味が無いという結果です。 確かに筆者は記憶のある限りインフルに罹った経験がありません。しかし以前は年に2回は必ず扁桃腺を腫らせていました。それが変わったのは睡眠時無呼吸の対策で、首の前側を緩めるようになってからです。そのおかげで唾液の分泌が多くなりました。風邪を引かない理由にこんな背景があったというのは驚きです。口腔からigAが沢山分泌されるのでしょう。
花王の顔|インフルエンザの「かかりやすさ」その差は唾液にあった

- #まもる #感染予防 #上気道バリア機能 #衛生学 #生化学
【特集:インフルエンザ】
インフルエンザの「かかりやすさ」その差は唾液にあった
あなたを守る「上気道バリア機能」の秘密(前編)
- 2020/01/22 Text by 堀川晃菜

今年も例年を上回るインフルエンザ感染拡大の傾向に、警戒感が強まっている。とにかく、インフルエンザにかかると、つらい。なんとかインフルエンザウイルスから身を守ることはできないか。
頑張る一人ひとりを守ることで、感染に強い社会を実現したい──そんな願いから始まった研究がインフルエンザ対策に新たな可能性をもたらした。
あなたの周りにも、風邪やインフルエンザに「かかりにくい人」に心当たりはないだろうか。
実はインフルエンザにかかりにくい人には、本人も自覚しにくい「秘密」があったのだ。
その新事実の解明に挑んだ花王の研究成果を前後編の2回に分けて紹介する。
今だけは……絶対かかりたくない!
受験生をはじめ、今だけは絶対にかかりたくない! と切なる願いを抱えている人も多いはずだ。こんな時、自分にもっと体力があれば……と思うが、実はアスリートでさえも、過度なトレーニング後の数日間は体調を崩しやすいことが知られている。
2019年9月に開催された花王ヘルスケアフォーラムでは、スポーツ医学、運動免疫学を専門とする国立スポーツ科学センターの枝伸彦氏が「高疲労・高ストレスが招く免疫機能低下と感染症予防」と題し、基調講演を行った。受験や試合など大事な時を控える人など「高疲労・高ストレスの人は、特に免疫機能の低下に注意が必要です」と指摘している。
2018~19年にかけて花王が行った調査からも、疲労とストレスの度合いが高い人ほど、風邪やインフルエンザに感染しやすいことが示された。そう、今、頑張っている人ほど要注意かもしれないのだ。そこで今回はインフルエンザ予防策の新たな一手として、「上気道バリア機能」の本来の働きを引き出す“秘策”を紹介していく。

- 【図1】インフルエンザに「かかりにくい」55人と「かかりやすい」54人、計109名を対象に行ったストレスおよび疲労の度合いと上気道炎(かぜ・インフルエンザ)の罹患との関係性。ストレスの程度は、視覚的アナログスケール(Visual Analogue Scale;VAS) により、直線状の左端をゼロ、右端を最大として連続的な数値として評価。疲労点数は厚生労働省が作成・公表している疲労蓄積度チェックリスト(※1)に基づき判定。ストレスや疲労が溜まっている人では、そうでない人と比べて、風邪やインフルエンザへの感染しやすさに有意な差があることが明らかになった。「かかりやすい人」「かかりにくい人」の判定基準については以下の本文中に記載する。
予防策を講じていても
おそらく、この記事を読まれている方は、日頃から予防に対する意識も高いのではないだろうか。手洗い、うがい、マスクに加湿器。子育て中の筆者もかなり警戒して気を付けている。
だが、そんな我々にとって、にわかには信じがたいデータがある。なんと「インフルエンザにかかりやすい人(群)には、かかりにくい人に比べて予防を多く行っている人が多い」というのだ。

- 【図2】図1と同じ母集団を対象に行った実態調査の結果。例えば、空気清浄機や加湿器の使用については「かかりやすい人」は半数以上が使用しているのに対し、「かかりにくい人」では半数以下という回答結果となった。
「えーっ、今までの努力は無駄だったの?」と叫びたくなるところだが、この結果の捉え方としては、どうも違うようだ。花王 パーソナルヘルス研究所の山本真士氏は次のように話す。
「これらの予防行動に効果がないということではなく、それでもかかってしまうほど、インフルエンザのかかりやすさには『個人差』があるものと考えられます。この結果は社内でも物議を醸したのですが、かかりやすい自覚がある人ほど、予防に力を入れているのだと捉えられます」

- 花王株式会社 パーソナルヘルスケア研究所 山本真士氏。大学では錯体化学を専攻。2001年、花王(株)に入社、ヘルスケア食品研に配属される。現在はパーソナルヘルスケア研で開発を担当。技術を製品として昇華させることに情熱を注いでいる。
花王ではこの調査の前段として、まず約1万9577人を対象とした調査をしている。ここでは「過去1年間に一度も風邪にかからず、過去3年間にインフルエンザにもかかっておらず、なおかつ感染症にかかりにくい自覚がある人」を「かかりにくい人」とし、反対に「過去1年間に3回以上風邪をひき、過去3年間に2回以上インフルエンザにかかり、なおかつ感染症にかかりやすい自覚がある人」を「かかりやすい人」とする基準を設けた。
その結果、「かかりにくい」に該当する人は、33%(6491人)、「かかりやすい」に該当する人は2%(405人)、どちらの条件にも該当しない中間層が65%を占めた。
図1と図2の調査は、この大規模調査で抽出された109名(前出の33%と2%に該当する人から選抜)を対象に実施し、前出の「インフルエンザにかかりやすい人(群)には、かかりにくい人に比べて予防を多く行っている人が多い」というのは、予防行動について詳しいヒアリングを行った結果だ。
繰り返しになるが、既存の予防法を否定するものではないことは重ねて強調しておきたい。厚生労働省やアメリカ疾病管理センター(CDC)が科学的な根拠があるものとして、ワクチンの接種、手洗い、咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ・ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえること)を推奨している。また、インフルエンザのワクチンについては「重症化を防ぐ」意味合いが大きいこと(※2)、うがいによる予防効果はインフルエンザについては科学的に証明されていないこと(※3)も追記しておきたい。
減る傾向にない患者数
さて、これだけ気をつけていても、依然としてインフルエンザが大きな脅威であることに変わりはない。厚生労働省によると、季節性インフルエンザの国内感染者数は年間で約1000万人と推定され、10人に1人が感染するといわれている。その数はいっこうに減る傾向にない。

- 【図4】2009~2019年における季節性インフルエンザの推定患者数(出典:薬局サーベイランス ※4)
こうした現状を前に立ち上がったのが、花王の研究者集団だ……! と言いたいところなのだが、最初はほんの数人の小さなチームだったという。そもそも「トイレタリーメーカーが、なぜインフルエンザ?」と不思議に思う人もいるかもしれない。
「もともと花王には、清潔・美・健康・環境という大きく4つの研究領域があります。その中間領域に、まだ取り組むべき課題があるのではないかということで、清潔と健康の間にある『衛生』領域に着眼することになりました。私は当時、ヘルスケア食品研究所に所属していたのですが、生物科学研究所、パーソナルヘルスケア研究所、それから事業部の人たちと一緒にアイディアを出し合っていく中で、公衆衛生の大きな問題であるインフルエンザに対して、独自のアプローチができないかという話になりました」(山本氏)
こうしてプロジェクトが始動したのが2015年。この時点では「抗インフルエンザ性」を示す有効成分の手がかりは、まったくと言っていいほどなかった。インフルエンザのかかりやすさに「個人差がある」といっても、あまりにも漠然としているが、その所以をどのように解明していったのか。
「かかりやすい人」「かかりにくい人」の差とは
研究チームが注目したのは「感染が成立するまで」の過程だ。インフルエンザは接触感染、飛沫感染、さらには空気感染が成立する。ウイルスとの接触を回避するのは、ほぼ不可能だろう。ならば、どうにか感染を瀬戸際でくい止めることはできないか。
「感染」とは、口や鼻、あるいは目の粘膜から体内に侵入したウイルスが細胞の中で増殖する状態を指す。主戦場となるのは「上気道」(鼻から鼻腔、副鼻腔、咽頭、喉頭まで)の粘膜だ。

- 【図5】インフルエンザの感染経路
当然、我々の体もみすみす敵の侵入を許しているわけではない。たとえば、唾液や鼻汁などに多く含まれる分泌型IgA(secretory immunoglobulin A; SIgA)は、粘膜免疫で中心的な役割を果たしている抗体だ。また血液中のIgG抗体も、ウイルスに対する感染防御に効果の高い抗体として知られている。(現在の注射型ワクチンは、主にIgG抗体を誘導するもので、血中から気道粘膜にしみでる抗体により感染が抑制されると考えられている。しかし、現行ワクチンでは分泌型IgA抗体を誘導できないため、感染の防御には限界がある。(※5)

- 【図6】粘膜上皮細胞においてインフルエンザの感染防御に関わる免疫細胞・免疫物質の例
こうした免疫機能の活性化を図るアプローチは、世界中で盛んに研究が続けられており、免疫のバリア機能に対する人々の関心も高い。だができれば、免疫部隊の出番を必要とする前に、もう一つ手前の段階で何かできないか。そう考えたのが花王の研究チームだった。
「免疫機能を高めることは非常に重要です。しかし、免疫に加えて何かできないか?と考えました。そこで粘膜上皮細胞にウイルスが到達するか、しないか、その瀬戸際に注目しました。それが『上気道粘膜上皮バリア機能』(以下、『上気道バリア機能』)です」と山本氏は話す。
「上気道バリア機能」とは唾液、粘液、繊毛における一連の生理機能を指している。たとえば、気管支に入り込んだウイルスなどの異物は、粘膜上皮細胞から分泌される粘液にキャッチされ、繊毛運動によって排出されることが知られている。ただし繊毛には寒さと乾燥に弱いという残念な弱点もある。

- 【図7】ウイルス感染から粘膜上皮細胞を効果的・持続的に防ぐ「上気道バリア機能」に注目
また、プロジェクトの開始当初(2015年頃)は、世界的にみても「上気道バリア機能」とインフルエンザのような上気道の感染症との関連についての学術論文は少なく、一般的にそれらは体を守る働きがあると言われているものの、その重要性を裏付けるデータが十分にあるとは言えなかった。
しかし、その中でも例外があった。唾液である。唾液に含まれる複数の成分がインフルエンザウイルスの防御に寄与する可能性(※6)を含め、いくつか報告があったため、山本氏らは、唾液に焦点を絞って研究を進めることにした。
唾液が少ないとかかりやすい?
具体的には、まず唾液の量を調べた。前出の「かかりにくい人」「かかりやすい人」(計109名)から、安静にした状態で唾液を採取。2分ごとに5回、唾液を採取し、全体の重量を比較した。その結果、インフルエンザにかかりやすい人は、かかりにくい人に比べて、有意に唾液の分泌量が少ないことが示された。

- 【図8】唾液分泌量の比較。上気道炎に「かかりにくい人」の安静時10分間の唾液分泌量が平均2.79mLに対し、「かかりやすい人」は平均1.95mLだった。
つまり、唾液の量が多いほうがかかりにくい可能性があるということだ。ならば、やはり唾液の中に、感染防御にはたらく成分がありそうだ。そこで次に唾液の「質」に注目した実験がなされた。
複数の人から唾液を採取し、それぞれ一定量をA型インフルエンザウイルスと混合した上で、実験用の培養細胞(※7)に感染させた。その後、「プラーク定量法」と呼ばれる方法でインフルエンザウイルスを可視化することにより、ウイルスの培養細胞への感染の程度を調べることができる。すると、同じ量の唾液を混合しても「ほとんど感染を起こさない唾液」と「多くの細胞が感染してしまう唾液」があることが明らかになった。
つまり、単に唾液がたくさん出ればいい、というだけではなかったのだ。ここにインフルエンザのかかりやすさにおける“個人差”の理由がありそうだ。唾液の「抗インフルエンザ効果」のカギを握る物質とは何なのか。そして、「質の良い唾液」にするにはどうしたらよいのか。
つつぎは<後編>へ。

- 【図9】 唾液による抗インフルエンザ効果の検証。抗インフルエンザ活性が高い「高活性」の唾液では、ほとんど青い部分(「プラーク」と呼ばれる」)が見られないのに対し、「低活性」の唾液では、唾液がない場合に近い状態まで感染していることが確認された。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
10月4日 価格変更の予告 今まで宣伝のために低価格で販売してきましたが、令和8年1月から価格改定します。¥300と¥350を¥580に改訂となります。
7月24日 睡眠時無呼吸症候群は放っておくと心臓に影響が及び、狭心症の発作に悩まされることになります。寝ているときに呼気が吐けない、無意識に努力して吐き出そうとするが、気道閉塞のためそれが出来ず、呼吸が出来なくなってしまします。この繰り返しが心臓に負担をかけ、いつしか狭心症の発作へ変わっていきます。これはあるときに急に訪れます。奥歯が痛いと思ったらその数秒後、左胸が締め付けられる痛みが襲ってきます。これはなかなか治りません。仕事で運転しているとき、急にこのようなことになりました。仕方なく路側帯に止めてしばらくじっとしていました。このまま行くとどうなるかは分ると思います。無呼吸は放っておいたら絶対ダメなんですね。
7月22日 首の前側を緩めることのメリットは何か? たまに寝ているときに寝違いが起こり、起きた時に痛い!となりますが、こういうときに無事でいられます。普段から緩めていると、首に不具合が起きたときに平気ですし、追突されてむち打ちになったときでも回復が早くなります。強くなったのではなく、柔軟性が出てきたからです。ここから肩、首に起こる頚肩腕症候群にも罹らずに済みます。身体の運動レベルも上がるでしょう。もっとも上肢の調整は必要ですが。めまいや無呼吸に止まらず、応用範囲は沢山あります。
7月14日 今まで言わずに来ましたが、ここで言っておきます。1ヶ月間無料のアンリミテッド会員登録は便利ですが、1ヶ月経つと課金されます。私の改善法は2~3ヶ月かかるのが普通ですから、その時には本がないということが起こります。細かいことも書いてありますので、購入して貰った方が良いと思います。
7月4日 本当に久しぶりですが、耳の圧迫感が出てきました。最近はやることが多くて、首のマッサージをやっていませんでした。これは、と思い首を緩めてみると、徐々によくなっていきました。圧迫感だけは嫌ですね。何とも気になってしまい、嫌な気分になると思います。右と左で聞こえる感じが違うのです。イライラしていたあの頃を思い出します。全くやらないよりは、たまにメインテナンスをする方が良いようです。本の中で重要項目として紹介しています。
2025年6月20日 ここのサイトからAmazonへ飛んでいく人が多いので、都度改訂するよりもここに書いた方が良いのかも知れません。
めまいにしても無呼吸にしても肥満の人が多いと思います。その解決策は、すばり植物油を断つこと。そして油は肉や魚から摂る。筆者は今から1年前に植物油をやめて、体重が大幅に減っています。一時期は68㎏ありましたが、今は60㎏です。体調が良い自己ベストは62㎏ですから、一気に改善したことになります。痩せるサプリなどは全く必要ありません。もし仮に不具合があればここで真っ先にお伝えします。現代人は油の摂りすぎだと言われますが、何でもかんでもで、お菓子の中にも入っており、油のないものは南部煎餅くらいです。
それから首の前側を緩める方法ですが、どうも指導の方法が難しいようで、色々考えました。喉仏を挟むようにして、ごく小さい範囲を緩めることから始めて段々大きくしていくのが良いと思います。いずれ改定時に載せていきたいと思います。
※ 睡眠時無呼吸と聴覚障害の関係に触れています。筆者も両方を同じ時期に発症しました。難聴もそうですが、めまい、耳の圧迫感など苦しみました。耳と呼吸器が近い位置にあり、相互に関連していることが示唆されます。繰り返しの試行によって既に分っていますが、その場所は上気道で、ここから耳へは耳管でつながっています。気道を確保するには喉の部分を緩めていくこと。サプリだけでは無呼吸回数が減るだけですから、ここの改善法を使って下さい。
※ コメントを付けて戴きました。嬉しさ一杯。自分では書けないんですよね。連絡できませんが、ありがとうございます。脳梗塞の症状より、めまいの方がもっと辛かったと思いました。
最近の広告によると『耳鳴りの原因は耳の中の腫れ』だそうです。こうやってずっと騙され続けたのに、また騙されようとしています。楽して治したいのは分りますが、そのようなお手軽な方法はありません。自分の身体の使い方が全ての原因ですから。
2024年10月25日に日本でレビュー済み
※ 変形性ヒザ関節症の本が削除されました。価格変更申請が問題だと思いますので後でまた出版したいと思います。どちらも解消まで2~3ヶ月はかかりますので、冬の今から取り組んでおいた方が良いと思います。
医療でも治らない病気が多くあります。無呼吸症はCPAPを外して初めて治ったということが出来ます。めまいは残念ですがなくす薬はありません。でも医療で治せないからといって全ての対処法が無効なのでしょうか。私の経験からいうと、医療で治せないからこの方法が有効だと言いたいのです。ここで紹介している方法は人の手を煩わせることなく自分で実施できるものです。何年も治らない重症の方をお待ちしております。
めまい ふらつき 耳の圧迫感 耳鳴りはどうして治りにくいのかを考察して、本当の解消法を提示します。薬や手術で治すものではなく、耳と関係のある部位を刺激することにより改善していくことが可能。今まで治らなかった人でも実施できます。予約受付中 7月29日発売 画像をクリック
後の世代が症状で困らないために! 周囲に困っている人がいたら教えてあげて下さい。
画像をクリック
※ 睡眠中に舌の付け根が下がる問題に対して、新たに舌筋肉をシェイプアップする方法を加えて増強しました。当サイトのテーマでもある『睡眠時無呼吸 めまい』何年にもわたって解消法を探してきました。その結果がここにあります。今も症状に苦しむ人に贈る、すべての知識と試行錯誤の集大成。
腱鞘炎が酷くなると何もしなくても痛みが襲ってきます。日常生活を痛みなく送るためには、速やかに解消することが必要です。
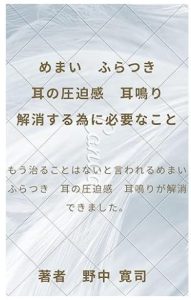
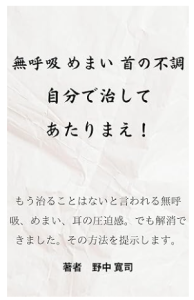
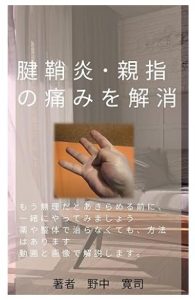
@nshinchan2786
1 日前